
リハビリテーション / 熱い水
■bandcampにてダウンロード版リリース ¥200
■Music Video
本場のAmapianoには到底なれない。それでも、自分たちの土の匂いと音を混ぜてみたかった。
コーラスで祈り、ギターで叫び、ウイスキーKAVALANに手を合わせるように生まれたこの曲の記録。
Amapianoをやってみたかった
この曲を作ろうと思ったきっかけは、ひとつの曲との出会いでした。
■Samthing Soweto / Hey Wena (feat. Alie-Keys)
Amapianoというジャンルに本格的に触れたのはそれが初めてだったと思います。
「ジャンル」への興味というよりも、この曲、キックがほとんど鳴ってないのに、どうしてこんなに身体が揺れるんだ?驚きが先にありました。
耳を澄ませていると、土の匂いが立ち上るような低音、どこか悲しみと祝祭が同居する空気感。深夜の自室でふと出会ってしまった音楽に、静かに胸を掴まれました。
その後、国内外のAmapiano楽曲やリミックスをあれこれ聴いてみたのですが、やはり惹かれるのは、「キックが弱い/ほぼ無い」タイプのものばかり。強く打ち鳴らす音ではなく、余白で躍らせる。その“躍らせないことで踊らせる”矛盾に、私は完全にやられてしまったのです。
ダンスミュージックというと、強いビートと煌びやかなグルーヴ、という印象を持つ方も多いかもしれません。でも、私が求めたのは「踊らせる音楽」ではなく、「揺れさせる空間」でした。拍のどこにも強過ぎる主張はなく、それでいて、なぜか心と体の芯が微細に動き出す。無音の行間に、音ではなく時間が揺れているような感覚。
この感覚は、若い頃にはわからなかったものかもしれません。年齢を重ね、表現に強さよりも繊細さを求めるようになって、ようやくこの音楽の輪郭が、自分の中に染み込んでくるようになった。そんな気がしています。
だから、やってみたくなった。Amapianoを。流行だからでも、誰かに褒められたいからでもない。自分の歩いてきた時間の重さと、いまなお燻っている熱を、強く鳴らさずに届ける方法としてこの音に賭けてみたかったのです。
プレステージ加藤とAmapiano
このジャンルで曲を作ってみたいと思い立ったとき、まず最初に相談したのが、長年の相方であるプレステージ加藤でした。
彼はLE SSERAFIMの熱烈なファンで、その中でも「Smart」という楽曲を特に高く評価していました。この曲にはAmapianoが取り入れられていて、世界のポップスの最前線にこの音が入ってきたという実感を彼なりに持っていたようです。思った以上にすんなりと賛同してくれ、この企画が本格的に動き始めました。
思い返せば、私たちが組んでからこうして完全に未踏のジャンルに飛び込むのは、実は初めてのことだったかもしれません。もちろん、これまでも色々なテイストに挑戦してはきましたが、Amapianoのように「世界的に新しく、かつ地理的・文化的背景が強いジャンル」に正面から向き合うのは今回が初でした。
そして、本場っぽく作る必要なんてない。むしろ、似合わない。私たちは南アフリカの出身でもなければ、20代の現行クラバーでもない。音楽に人生のすべてを賭けてきたわけでもなく、むしろ一度降りて、そこからまた静かに戻ってきたような存在です。
そんな私たちが、Amapianoをそのままトレースしても、魂が入らない。必要だったのは、Amapianoを通して己を映すことだったのだと思います。
どこか哀しげで、でも踊れる。声高ではないけれど、じわじわと沁みてくる。そんな音楽に、自分たちの年齢や温度、生活のリズムを溶け込ませられたらと、そういう方向性で、迷わず舵を切ることができました。
完成した音は決してリアルなAmapianoではありません。でも、私たちが生きている場所でしか生まれえなかったAmapianoにはなったと思っています。
コーラスと歌
この曲を作り始めた当初、「音を詰め込まない」という方針でした。Amapianoに対して抱いていた個人的な理想像──つまり、“少ない音数で、深く揺らす”というスタイルを、自分たちなりに追求してみたかった。
ただ、その選択は、当然ながら何か別の方法で空間を支えることを意味します。私たちが選んだのは、「声を重ねる」という、ある意味もっとも人間的な手段でした。
3声、あるいは4声。時にユニゾンで芯をつくり、時に和声のずれを活かして空気を濁らせる。「この小さなズレが、聴き手の呼吸にどんな影響を与えるだろう」そんなことを考えながら、幾重にも重なるコーラスを配置していきました。
ダイナミクスが単調になることを恐れていたのではありません。むしろ、“単調であること”がどこか安心感や深さを生む場合もあると理解した上で、それでも、その“単調さ”を意識的にたゆたわせるような設計を目指していました。
若い頃は、歌の上手さや声量が多くの要素に優先し、嫉妬する時期もありました。けれど年を重ねるにつれ、声とは残響の質なのだと、少しずつ思うようになりました。発した声そのものよりも、それが空間にどう残るか。その“残り香”のようなものが、聴き手の内側に波紋のように広がっていくのだと。
今回の曲では、まさにその「残響」で空間を描きたかったのだと思います。そして、それは単なる技術的なアプローチではなく、生き方そのものの話でもありました。
声を重ねるという行為には、「人が寄り添い合う」という意味もあるように思います。無理に響かせるのではなく、ただそっと並んで、同じ空気を震わせる。そういう時間が、この曲の奥に流れていてほしいと願いながら作業を進めました。
兎白えむとの出会いと、予定外の“主旋律”

曲の原型が出来上がったとき、まず感じたのは、この音に、男2人の声だけでは届かない領域があるということでした。
どこかが足りない。空気の密度はあるのに、抜けきらない部分がある。まるで硬質なグラスに水だけを注ぎ込んだような、透明だけれど拡がらない手触り。
女性の声が必要というより、「もうひとつの質感」が必要だったのだと思います。言葉の意味よりも前に、声そのものが風景を変えてしまうような、そういう響きが。
そうして思い浮かんだのが、兎白えむさんでした。これまでのやり取りの中で、彼女の声の持つ「揺れ」や「間」の美しさを何度も目の当たりにしていたこともあり、この人にお願いすれば、間違いなく曲が一段深くなる、そんな確信めいた感覚が、自分の中にありました。
当初は、あくまでデュエット。つまり、あくまで私たちの曲に、彼女が加わるというバランスを思い描いていたのですが、いざレコーディングが始まると、その想定はあっさり覆されました。
彼女の声が、音の間を滑るようにして入り込み、気づけば、主旋律は彼女のものになっていた。それは奪われたというより、委ねられたという感覚に近かったのです。
曲の中心が変わってしまうことに、ほんの少しの戸惑いがなかったと言えば嘘になります。けれど同時に、きっと正しい変化なんだとも思えました。主役を奪い合うような世界ではない。この曲には、彼女の声が重力として必要だったのです。
音楽は、理屈で整理された均衡よりも、無意識の中で起こる主従の逆転や予定外の美にこそ本質が宿る気がします。今回のケースはまさにその好例でした。
兎白さんの声が中心にあることで、曲全体がひとつの語りになった。それはデュエットというよりも、私たちの祈りを、彼女の声がひとつにしてくれたという形だったように思います。
結果として、正解でしたし、それ以上に、曲そのものにとっても、ひとつの必然だったのだと思っています。
クライマックス
この曲の終盤。いわゆるクライマックスと呼ばれる場所に、私はどうしてももうひとつの要素を置きたくなりました。それは、派手な転調などではなく、ささやかなズレとして響く声。メインボーカルとは別の場所から、語りかけてくるようなラインです。
そこで、このオブリガートを何に託すかと考えたとき、自然と浮かんだのがプレステージ加藤でした。彼の声質には、主張しすぎない謎の力がある。それでいて、時折ふと滲むように意志が顔を覗かせる瞬間がある。そのバランスが、この曲の最後に必要だと思ったのです。
ピアノとほぼ同じ動きをしながら、ほんのわずかにメロディやタイミングをズラす。音価の端に微細な揺らぎを生ませることで、交わるようで交わらない関係性を築く。オブリガートとしては、かなり繊細なバランスを求めたラインでした。
でも、加藤はそれを難しさとしてではなく、身体の感覚として、素直に受け止めたように感じます。それは彼の持つミュージシャンとしての直感であり、たぶん、私がいちばん信頼している部分でもあります。
録音を終えて初めて全体を通して聴いたとき、そのオブリが、メインメロディに絡むでもなく、対抗するでもなく、
別の人生からやってきたもうひとつの声のように聴こえた瞬間がありました。
それは、自分でもかなり気に入っている部分です。
音楽というのは、結局のところ、複数の声が交わらずに併存することをどれだけ許容できるか、あるいは、交わらなかったことをどう物語にできるか、という芸術でもあります。
この曲のクライマックスでの加藤の声は、まさにそれを象徴する存在でした。主旋律の外で、語るような声。誰にも届かなくても、そこにあったことだけは確かだという証。
各パートについて
ログドラム≒ベース
Amapianoにおいて、ログドラムと楽曲全体の関係は、いわば重力と地平線のようなもので、一方が存在するからこそ、もう一方の存在感が際立つ、そんな印象を持っていました。
今回の制作では、その基盤となる部分に迷いがありました。音作りの段階から、ログドラムの鳴らし方、サブベースの質感、タイミングの微調整、どこをとっても手探りで、「これで正解なのか?」という不安が終始つきまとっていたのです。
Amapianoの文法に忠実でいようとすればするほど、どこかで自分の中に「この音は自分の生活から生まれていない」という違和感が残る。その違和感を無視して作業を進めれば、曲がただの模倣品になってしまう。
結局、途中からはあえて粗さを残す方向に舵を切りました。結果的に、ログドラムは主張しすぎず自然な存在感に落ち着きました。誰かの注意を引くための音ではなく、音楽が壊れないように支えてくれている無名の骨組みのような響きです。
最終的なミックスが終わるまで、この部分にはいまいち自信が持てませんでした。若い頃なら、迷いを「失敗」だと感じていただろうし、より強気な音を鳴らしていたかもしれません。でも今の自分には、迷いながら選んだ音にしか宿らないリアルがある。
パーカッション
「キックに頼らず、身体を揺らせる曲にしたい」
それは言い換えれば、ダンスミュージックの中核をあえて外すという、矛盾のような挑戦でもありました。
クラブで鳴る音楽やメジャーな曲は、たいていの場合、キック・バスドラムがリズムの軸になります。人を踊らせるには、それなりの重みと圧が必要だと、多くの現場で学んできました。でも今回、自分の中に芽生えていたのはその“逆”でした。
軽さの中で揺れること。空白の中にリズムを見つけてもらうこと。そういう音楽をやってみたくなったのです。
キックは極限まで削ぎ落としました。そのかわり、パーカッションを好き勝手に敷き詰めるという手法に出ました。
ログドラムを中心に据えつつ、ボンゴ、コンガ、ティンバレス・・・Amapianoの本場では使われていないかもしれない音たちも、自分が聴きたい音かどうかで選びました。
音源ライブラリやサンプルは山ほど漁りました。細かいクオンタイズのズレも許容するようにしました。機械の精密さではなく、人のリズムに近いもの。
やりすぎた部分もあると思います。引き算をもう少しスマートにできたかもしれないし、音数やバランスも、冷静に見ればもう一段洗練できたはずです。
時間にも精神的な余裕にも限りがある中で、最終的には今の自分が面白いと思える配置になっているかどうかを基準に判断しました。正しさよりも楽しさ優先です。
コード進行 – 陳腐さに挑む
昔からコードをループし続けることに、耐えられない人間です。これは、ダンスミュージックを作る上では、かなり致命的な欠陥です。
反復によってグルーヴを生み、少しずつ変化させながら快楽の密度を高めていく、その構造の美しさは理解しています。むしろ、リスナーとしては深く敬愛すらしている様式美なのに。いざ自分が作り手になると、何かを変えたくてたまらなくなる。同じコードが8小節続いただけで、なぜか落ち着かない。「ここでひとつ、意外な動きを・・・」と、つい余計なことをしてしまう。それは、若い頃からずっと変わらない性分です。
今回の『熱い水』でも、その衝動は何度も顔を出しました。それでも、今回はかなり我慢したほうです。全体の構成はこれまでよりシンプルに、どこかわかりやすさを意識したコード進行にしています。
わかりやすさを恥じないこと。これは、40代に入ってから身につけた、ひとつの覚悟のようなものです。音楽を難解にして自己防衛するのではなく、むしろ、聴き手に一歩近づくことのほうがよほど難しく、誠実で、そして勇気のいることだと知ったのです。
だから、あえてあるあるな進行も選びました。陳腐と呼ばれることを恐れずに、その中でどれだけ自分の色を滲ませられるか。それが今回のひとつの挑戦でもありました。
そして迎えるクライマックス。ここでは振り切りました。これが俺たちの皮肉だと言わんばかりに、あえてベタで、使い古されたような進行を持ってきた。でもそれは、投げやりな挑発ではありません。こんなにもありふれた響きで、まだ気持ちよくなれるのか?という問いを、音で投げてみたかったのです。
ありきたりを、もう一度信じること。予定調和の中で、もう一度体温を感じてみること。そこにこそ、音楽の本質が宿る瞬間があると信じて手を伸ばしてみた。
ギター
この曲を作り始めた頃、ギターはあくまで添え物程度に考えていました。空間を少しだけ彩る、枯れた音のリフを1、2本。あくまで引いた立ち位置で、全体の温度を保つような使い方になるだろうと。
いざ作業を始めてみると、その枯れた予定は、あっさりと破綻しました。
空間系エフェクトを重ね、歪ませ、チョーキングし、スウィープして、時にノイズのように、時に泣きの要素を、これまで避けてきた手法、見ないふりをしてきた音作りの数々を、全部やってしまえと、自らに許していく作業になっていきました。
その過程は、音楽制作というよりも、むしろ何かを弔っていくような行為に近かったかもしれません。
カバランのウイスキーを生み出した職人たちが、厳しい環境の中で試行錯誤を重ね、「美味しい」の一言のために人生を注ぎ込んできたこと。その背景を知ったとき、ふと自分に問いかけてしまったのです。
自分は、これまで何を賭けてきただろうか。
何かを磨いてきたと言えるのか。
「美味しい」と呼ばれる瞬間のために、何かを捨てたことがあったか?
■参考曲
答えは、恥ずかしいくらいにあやふやでした。音楽は好きだった。でも、それだけだったのかもしれない。そんな後悔や疑念を、ギターという手元の刃に込めて、ひとつひとつ、トラックを重ねていきました。
ローDで唸る低音、ハーモニクスの断片、スライドとノイズが入り混じるリフ。どれもが、音楽の神様に振り向いてもらえなかった自分の、ささやかでみっともない抵抗だったのだと思います。
今さらテクニックをひけらかすつもりはない。ただ、これまでやってこなかったこと、カッコ悪いからと避けていたことを、いっそ全部入れてしまおうと。カッコ悪さを肯定する音があってもいいじゃないか。そんな気持ちで、音を重ね続けました。
Amapianoの文脈において、このギターの入り方は完全に異物だと思います。ある意味、空気を読み損ねている。でもそれでいい。むしろ、その異物感こそが、この曲にもうひとつの熱を与えてくれるのではないかと本気で思っています。
鳴らした音がどう評価されるかは、わかりません。けれど、あのとき指を動かしていた自分には、たしかに嘘がなかったと信じています。
ピアノ、オルガン、シンセ – 冷静と混乱のはざま
ギターのパートがあれほどまでに奔放で、感情の奔流そのものであったのに対し、ピアノ、オルガン、そしてシンセサイザーのセクションは、ある種の冷静さをもって構築していくことができました。感情を爆発させるのではなく、構造として音を置いていくような、あくまで設計図と対話するような作業だったと思います。
ここでの鍵は引き算でした。全体のバランスの中で、主張しすぎず、しかし空間の湿度や奥行きを保つために、どのタイミングで何を鳴らすか。何を鳴らさないか。そういった細かい判断を積み重ねることが、課された役割だったように思います。
結果としては、トラック数を増やしすぎてしまった。「ここでこの音が出てきてくれたら」と願った瞬間に限って、なぜかその音が他の要素に埋もれてしまっている。そういうことが何度かありました。
音を鳴らす、という行為には、居場所をつくるという意味があるはずなのに、いつのまにか、自分で自分の居場所を塞いでしまっていたような、静かに陥っていた矛盾とでも言えばいいでしょうか。
冷静に作ったつもりの音が、全体の中で飲み込まれていく感覚。これは、音楽に限らず、中年以降の人生そのものにもどこか似ています。「ちゃんとやったのに、伝わらない」「存在していたのに、気づかれない」そんなふうにして、何かがフェードアウトしていく時間。
もちろん、それは次への課題としてきちんと受け止めるべきです。もっと少ない音数でも輪郭が立つように、鳴らす勇気だけでなく鳴らさない潔さも、これからはより研ぎ澄ませていきたい。
控えめに敷いた音が、最後の最後で意味を持つ。そんな曲が書けるようになったら、またひとつ、音楽との距離が縮まるのかもしれません。
「熱い水」とは何か?
『熱い水』というタイトルには、台湾のシングルモルト・ウイスキー「KAVALAN」への、ささやかな敬意が込められています。
一般的に、ウイスキーといえば冷涼な土地で熟成されるもの、というイメージが強いかもしれません。スコットランドの霧や、アイリッシュの湿度の中で時間をかけて育まれるもの。けれどKAVALANは、その常識とは真逆の、亜熱帯の台湾で生まれた銘酒です。
高温多湿な環境、熟成が早すぎるリスク、繊細な調整が求められる製造工程。そうした不利とされる条件の中で、それでも、いや、だからこそ世界に衝撃を与えるクオリティにたどり着いたという、その背景に、私は音楽という営みに通じるものを強く感じたのです。
KAVALANについて語るPodcastを耳にしたとき、そこにはウイスキーの話を越えた「精神」がありました。ジェンダーに対する自由な意識、真の多様性を許容する社会の空気、誰かに強制されることなく「こうありたい」と思える個の選択が許されている土壌。そしてそれが、KAVALANの酒の味に、不思議と結びついているような気がしてなりませんでした。
喉が焼ける。でも、その痛みの奥に、芯のような甘みがある。それはまるで、社会に生きる痛みの中から、それでも自分の美しさをすくい上げるような味わいです。そんなウイスキーを飲んだとき、「ああ、これを音で表現できないか」と思ってしまったのは、たぶん酔いのせいではなかったと思います。
水は、命を保つもの。でも、「熱い水」は、ただの栄養ではない。身体に沁みながら、心を少し焦がす。何かを奪い、何かを目覚めさせてしまう。そんな液体を音で鳴らせないかと、本気で思ったのです。
もちろん、無茶な願いだったことは自覚しています。ウイスキーの深度や香り、経年と偶然の積層を、音の分解能で再現できるわけがない。でも、その無理を承知で向き合うことこそが、この曲を私たちのものにしてくれたような気がしています。
KAVALANはひとつの象徴でした。あの酒に宿る「熱」のようなものを、どうにか音に宿せないかと、最後の一滴まで試した記録。それがこの曲『熱い水』です。
願わくば、この音があなたの耳を通して、静かに、けれど確かに、どこかを少しだけ焼いてくれますように。

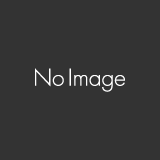

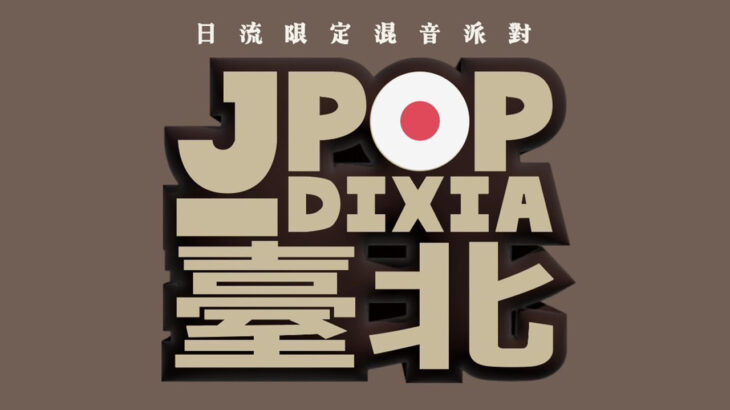

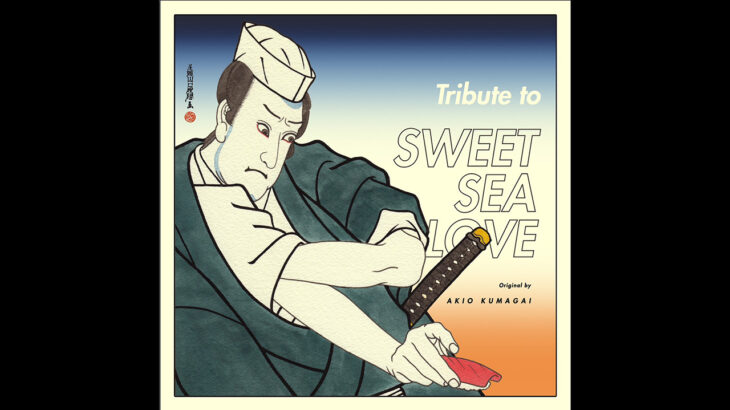

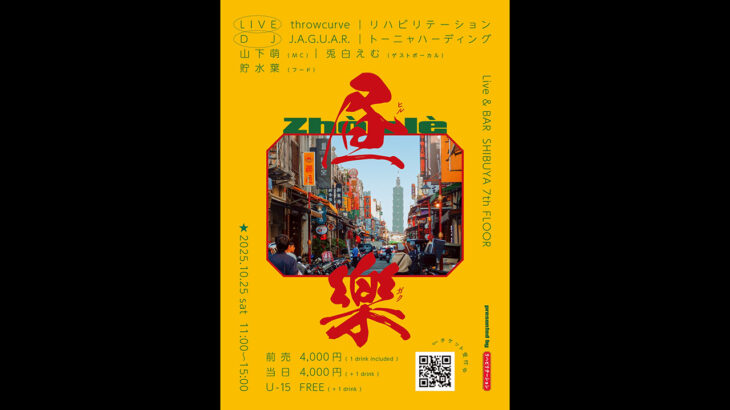
コメントを書く